遠隔運用に移行すること
流行性感冒により様々な場面での遠隔運用が余儀なくされています。しかし困ったことに、これまで対面で行うことを前提としていたことさえも、遠隔作業に移行しなければならなくなりました。
ここで、NIMTAこと私の周りの人々に訊いて回った困りごとをご紹介いたします。加えて、私見ですが考えうる解決手法を併記いたします。
困りごとあれこれ
ほぼリテラシー不足
パソコン教室化
状況:音楽レッスンなど
そもそも、テレ・ワークなりテレ・レッスンなりを始める前に、パソコンの使い方から教える羽目になってしまうという問題です。しかもZoomなどのビデオ・チャット・ソフトをインストールする方法・・・という次元でなく、「スタートメニューとは何か」から始めなければならないという話です。

解決方法:あきらめてPC教室から始める。
こればっかりは端末の使い方から始めないとどうにもならないので、PC教室を始めましょう。あきらめというより、こういったビデオ・チャットや配信を標榜した講座や教室が増える予感がしています。
OS・デバイス違い
状況:音楽レッスンなど
クライアント、つまりユーザそれぞれのデバイス・OSがばらばら。自分の知らないデバイスやOSでの操作方法など説明のしようがありません。そうでなくとも、PC、Mac、Android、iPhoneなどのプラットフォームでそれぞれ微妙に違うため、トラブルシューティングが大変です。自分が使っていないOSのトラブルは再現もできないため、解決を図るのはとても難しいですね。

解決方法:こういう時こそググる方法を教える。
PC教室を卒業したら自分で調べ、模索する方法を伝授します。こうすることでトラブルシューティングが容易になります。
マイクロホンの問題
状況:合唱の練習、音楽レッスンなど
マイクロホンが環境音を拾ってしまう。これはおそらく、無指向性のマイクロホンを使っているせいだと思われます。ヘッドセットやステレオマイクの一部は無指向性が使われており、マイクの向きを気にしなくてよいことなど、使い方が簡単なのがよいところです。しかし、どうしても狙っていない音も拾います。

解決方法:マイクロホンをアップグレードする、使い方を覚える。
少なくともマイクロホンはマイクロホンの形をしていれば良いというわけでなく、目的に合わせて選び、使い方を工夫すれば、良い音が録れます。こういった道具は安価・高価によらず使い方次第です。
ソフトウェアの問題
状況:音楽レッスンなど
いくつかのビデオ・チャット・ソフトウェアは設定を変更することでビデオや音声の送出クオリティを高めることができますが、できないものもあるようです。特に、ノイズリダクションが悪さをして、ノイズ以外の楽音をも消し去ってしまったり、ロングトーンが乱れるなどの弊害があるようです。
解決方法:ソフトウェアを変える、アップデートを待つ
設定が変更できないソフトウェアはそういう設計思想なので、より目的に合ったソフトウェアに乗り換える方がサービスの品質を上げることができるでしょう。ソフトウェアはそのうち使いやすくなったりするので、開発者の方にフィードバックと感謝を送りましょう。
トラブルの状態を説明できない
状況:さまざま
自分の環境でどういった問題が起きているのか把握・説明できないこともあるようです。つまり、何がどうなっているのかリモートでは説明できないということです。

(極地での不法投棄はやめて!)
解決方法:お手上げ
根気よく聞き出すか、その人の家に行って代わりにやってあげる意外には、特に解決方法はありません。全てリセットして最初から指示しながら環境を構築してもらうしかなさそうです。もしくは、最小限度の構成を持つスマートデバイス頼みになります。
リテラシーはあっても・・・
リテラシーのあるはずの大学の情報系学部でも以下のことが起こっているようです。
フィードバック不足
状況:大学の講義、合唱の練習など
普段の講義や合唱練習であれば、講師や指導者などの「話す人」は聴衆の様子を見ています。その際に話のペースや内容までも変化させることで聴衆の理解を深めることができていました。ところがビデオ・チャット・ソフトを通じた講義の場合、そうした対面で得られていた情報が格段に少なくなり、話を聞けているのかわからないために、双方にとって利益のないハイペースになったりするようです。

解決方法:ビデオやチャットを通じてフィードバックを送る。
音声に割り込むとチャットルーム全体に影響があり、また文字のチャットでは冗長だったりチャットのタイムラインが流れてしまうなどの弊害があります。このような場合、ビデオ越しにうなずいたり手を振ったりするのが大変であれば、ライブなどで使う団扇のようなサインを用意してもいいと思います。尤も、ソフトの進化は速いのでそのうちより良いフィードバック方法を持ったソフトが出てくるでしょう。
想像力不足
状況:情報系大学の学生による発表
これは先ほどのフィードバック不足に近いものがありますが、普段の講義のみならず学生の行う輪講などでは講師や教授よりもさらに慣れていない学生がしゃべります。このためペースが異常なハイペースになったり、あるいは説明不足になる傾向があるようです。しかもこれを指摘するとなるとその輪講や講義に参加している人全員の時間を止めることになるため、とても憚られます。
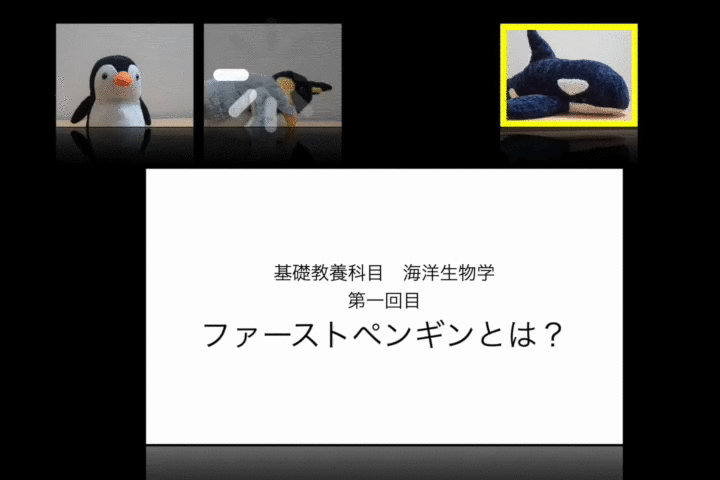
解決方法:ルールを設けてしまう、資料を全て配布し追えるようにする等
講義がハイスピードにならないよう、スライドの内容量やスライド一枚の表示時間を決めてしまうのも一つの手であると思います。または、資料を全て配布するなどの方法をとれば、それぞれのペースで講義を聴くことができると考えられます。
回線種別のごった煮
回線がポンコツ
状況:さまざま
回線がポンコツな場合です。特にCATVやADSLなどの旧来の回線は貧弱なこともありますが、光でもプロバイダによってはかなり貧弱なところがあるようです。次項とも関連しますが、貧弱な回線ではビデオ・チャットのようなトラヒックの大きな通信を連続的に使用することができず、「回線状況悪化」などのメッセージとともにチャットルームやビデオチャットのクライアントが閉じてしまうこともあるようです。特に、4Gなどの無線通信は時間帯にも、またその端末の位置にもよりますが、ビデオ・チャットを行うには非常に不安定です。同様にWifiも設置場所の状態によってはビデオ・チャットができないこともあります。

解決方法:プロバイダ、回線種別を再検討する
こればかりは住んでいる地域によって異なるので一概には言えませんが、インターネット回線を再検討する必要があると考えられます。特にリアルタイムの配信やレッスンなど、送出側や双方向になると見ている方にもストレスを与えます。
トラヒックの増大
状況:さまざま
前項とも共通しますが、固定インターネット回線では朝や深夜帯の回線速度が早くても、日中や夕方になると猛烈に遅くなるという現象があります。これは回線の種類や回線の繋ぎ方、つまり家からインターネットのネットワークに至るまでの繋ぎ方によるので一概には言えませんが、同一、あるいは近くにいるコンピュータが回線の食い合いを起こし、速度低下やレイテンシ増大につながっているようです。

解決方法:回線をアップグレードする。
たとえばADSLやCATVを使っているのであれば、光回線に乗り換える。光回線であればプロバイダを再検討するなどの対策が考えられます。時間帯による混雑は光回線でもベストエフォート契約にはつきものです。少々値は張りますが、最低速度がギャランティされる契約に見直すなどの方法が確実です。
解決方法はありやなしや
「読・書・算盤・ITスキル」となる?
今やパソコンよりもスマートホンなどのスマートデバイスの方が普及・浸透しています。スマートデバイスはディスプレイにカメラやマイク、通信装置が内蔵されていますから、最小限の配信環境はスマートデバイスだけで完結しています。
しかしながら、その配信品質も最小限ですから、品質向上には様々な手法があります。その一つがリテラシーの向上ですが、リテラシーといっても今回の場合はハードソフト両面知識がないと解決できない事柄ばかりです。特にITスキルはメディアリテラシーの一部にしかすぎません。

また、ソフトウェアは日々進化するし、ハードウェアもそこそこ日進月歩の状態です。日々新たな知識と、使うための技術を向上させる必要がありそうです。
聴いてる人のこと気にしてる?
大学の講義でも、合唱のレッスンでも、ウェブセミナーでも、聴いている人のことを気にしているのか?という問いです。
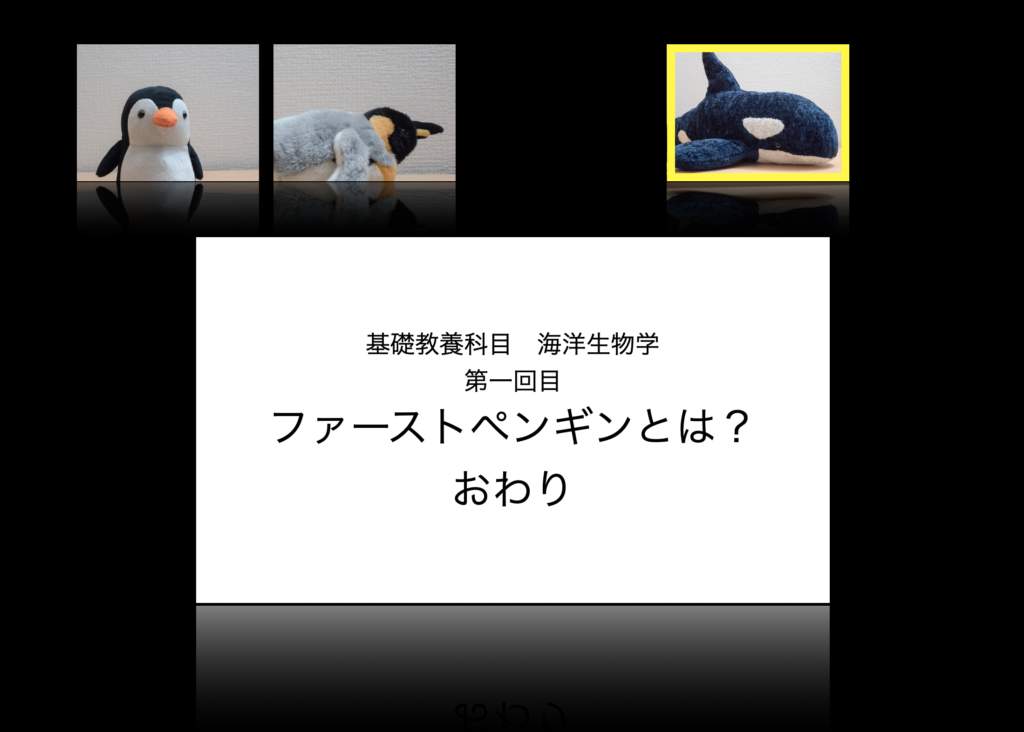
配信できたまではいいが、どの程度の品質、あるいは聞きやすさ、理解しやすさなのかは、聴衆それぞれの主観によります。今後は頻繁にフィードバックをもらえるよう働きかけた方が良いと思います。何人もの講師が発表するような場合は、厳格なルールを適用した方が、聴衆と講師の双方にとって利益になりそうです。
回線問題は結構喫緊
最近話題にのぼり、すでに東京の一部などでは商用サービスが始まっている5G回線ですが、5G回線は何もこれまでの通信環境を全て凌駕するという物ではありません。5Gは光回線の品質を無線で提供するというだけのことです。ともすれば、光回線が輻輳状態に陥るほどの通信を前提とした世の中になってしまうと、5G回線も同様に輻輳状態に陥ると思われます。
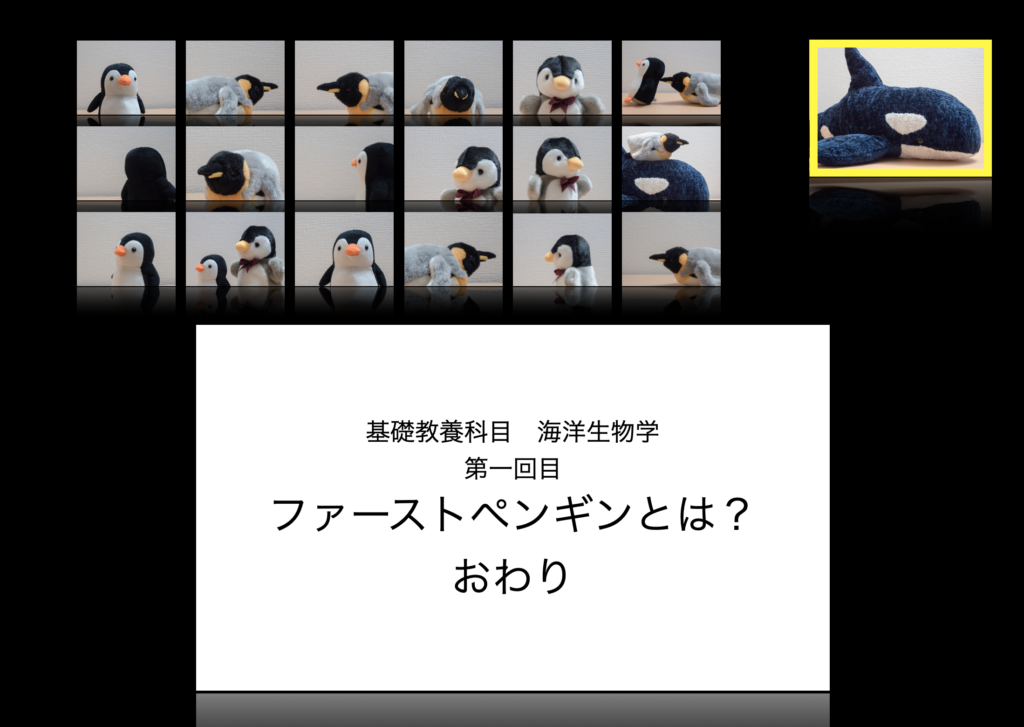
こればかりは個人でどうすることもできませんが、映像など大容量メディアを扱う企業ではすでに対策を始めています。
PRONEWS – ビデオ配信サービス、帯域幅の使用量削減作戦
MONOist – いまさら聞けない「エッジコンピューティング」
まとめ
取材を通してはじめてわかったことですが、リモート時代の困りごとは様々な側面からストレスを誘発していることがわかりました。
しかしながら、通勤通学の満員電車や、息苦しいオフィス、昼食難民などの過大極まるストレスから逃れたという事例もありますから、広く世の中に浸透して欲しいと思いました。




コメント